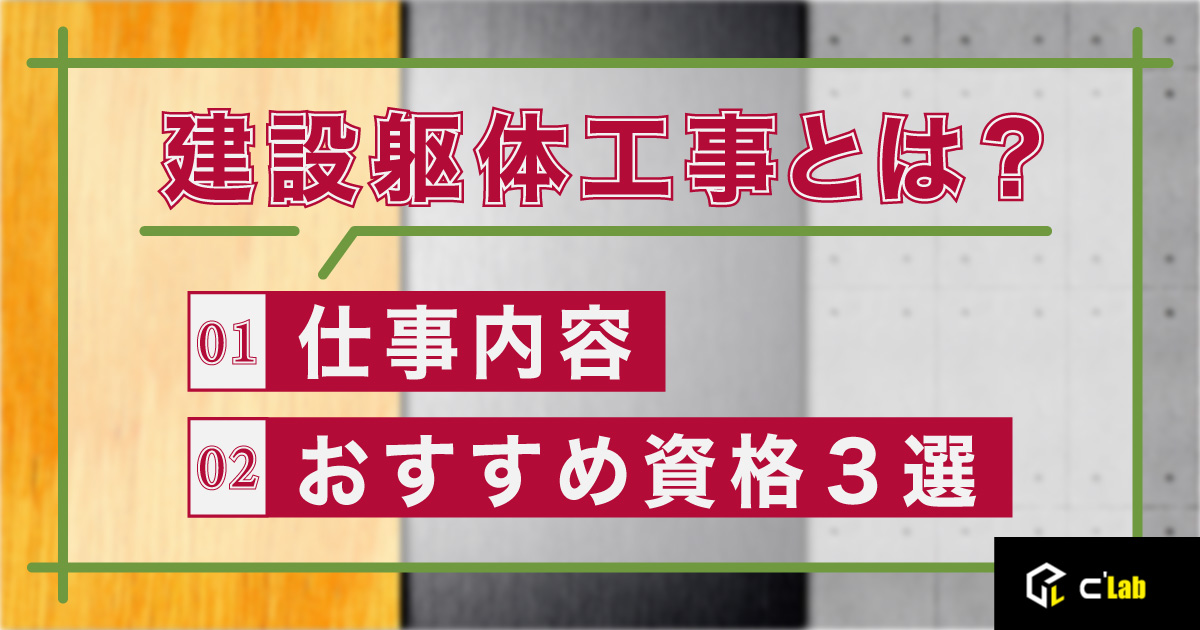
建物をつくる上で外すことのできない、建設躯体工事。
この記事では躯体工事の意味や仕事内容、躯体工の方におすすめの3つの資格についてお伝えします。
建設躯体工事とは?
建設躯体工事は、杭工事、基礎工事が終わった後に、建物の本体部分を作る工程です。工事によっては、「躯体工事は工期全体の70パーセント以上を占める」とも言われています。
メインの構造を形づくる大切な工程であるため、施工管理者にはコンクリート、鉄筋、鉄骨など、豊富な知識が必要とされます。
そもそも躯体とは何かというと、建築物の構造体のことを指します。基礎や柱、壁、土台、床版、屋根版などのことです。
この構造体に何の材料を使うかによって、木造、鉄骨造、RC造( 鉄筋コンクリート造)、SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造)などに区分されます。そしてその区分は、建築物の耐久・耐震・耐火・防音・気密性などに影響してきます。
これらの「躯体工事」に対して、塗装工事など内外装の仕上げのことは「仕上げ工事」と呼ばれています。
建設躯体工事の3つの仕事
躯体工事には、3つの仕事があります。
・鉄筋工事
・型枠工事
・コンクリート工事
それぞれの仕事の具体的な内容を、簡単にご紹介します。
鉄筋工事
鉄筋工事は、建物の骨組みを鉄筋で組む仕事です。
鉄筋工事の作業員たちは、鉄筋工と呼ばれます。
鉄筋工は、現場で渡された図面に沿って、「ハッカー」という専用工具を使い、鉄筋が交わる部分を結束線で固定し、鉄筋を張りめぐらせていきます。
現場での結束作業のほかにも、図面から必要な鉄筋の形状・寸法・数量などが記載された加工帳を作成する仕事、加工場で鉄筋を加工する仕事などもあります。
鉄筋は後でコンクリートのなかに含まれてしまい、建物が解体されるまで表に出てくることはありません。しかし、建物の構造力学的にとても大切な作業となります。
近ごろでは、機械や重機の使用によって、女性の鉄筋工も活躍しているようです。
型枠工事
型枠とは、建物の形となる、コンクリートを流し込むための木製の枠のことです。
型枠工事は、鉄筋工事が終わっている段階で行なわれます。型枠をつくって、その中にコンクリートを流し込み、壁などをつくる作業です。
型枠工事では、図面から寸法や形状を読み取って、加工図を作成します。
加工図をもとにベニヤなどを使用し、多くは工場で加工したものを現場に運び込んで、鉄筋の周りに組み立てるのです。中には、再利用性の高い鋼製型枠を使うこともあります。
型枠は、鉄筋を挟むようにつくっていきます。型枠と型枠の間にコンクリートを流していくと、コンクリートは鉄筋を含みながら、型枠どおりの形に流れていきます。コンクリートが乾いたら、型枠を取り外します。
このようにして、鉄筋が内側に含まれているコンクリートの壁などができあがります。こうしてつくられたものは、鉄筋を入れないコンクリートよりも、はるかに高い強度をもちます。なお、このような工法は、RC(鉄筋コンクリート)と呼ばれています。
一定の範囲以上にコンクリートにゆがみが出ると、建物の強度や出来映えに大きな影響を与えるため、型枠にずれやゆがみは決して許されません。そのため、型枠工事の職人の作業には精密さが求められ、一人前の型枠大工になるには「10年はかかる」と言われています。
コンクリート工事
コンクリート工事では、生コンクリートを打ち込みます。
前工程の型枠工事とコンクリート工事は、どちらも型枠大工と呼ばれる職種の人によって行なわれます。
現場に運ばれてきた生コンクリートにコンクリートポンプ車で圧力をかけ、型枠内に流し込みます。「バイブレーター」と呼ばれる機材を使い、型枠に流し込んだ生コンクリートに気泡ができるのを防止し、型枠の隅まで行きわたるようにします。
コンクリートを流し込む前に型枠に散水することで、コンクリートの接着がよくなります。また、型枠面を湿らすことによって型枠がコンクリートから剥離しやすくなり、表面が綺麗に仕上がります。さらに、しめ固め作業、ならし作業などの工程を踏むことで、表面が綺麗で、密度の高いコンクリートとなります。
流し込んだコンクリートが固まると型枠が外され、建設工事の工程は、塗装工事などの仕上げ工事へと移ります。
躯体工の方におすすめの資格3選
躯体工事を行なうために必要とされる、特別な資格や学歴はありません。土木科や建築科を卒業していなくても、建設会社に入って1から技術を身につけられるので、未経験でも安心なのが躯体工事です。
ただし、スキルアップや仕事の幅を広げるために、資格を取ることを視野に入れるのもよいでしょう。
このセクションでは、躯体工の方におすすめの資格を3つご紹介します。
建築工事施工管理技士
まず最初にご紹介するのは、建築工事施工管理技士です。職長など管理者としてキャリアアップしていくのに有利な資格です。
職長については詳しく知りたい方にはコチラの記事もおすすめです!
・施工計画の工程管理
・品質管理
・原価管理
・安全管理など
このような建設工事全体の進行を管理する役割を担うのが、建築施工管理技士です。
国家資格である建築施工管理技士には、1級建築施工管理技士と2級建築施工管理技士があります。そのうち、2級建築施工管理技士には、建築と躯体、仕上げという種別が設けられていて、鉄筋工事業では躯体を取得すると、主任技術者や専任技術者になることができます。
1級も2級も、学歴によって異なる実務経験が必要です。建築に関してこれまで学んだことがない人の場合、1級建築施工管理技士はハードルが高いため、2級建築施工管理技士の取得から目指すことをおすすめします。
鉄筋施工技能士
2つ目にご紹介するのは、鉄筋施工技能士です。この資格は、国家検定制度である技能検定の1つとなっています。
鉄筋施工技能士には、2つの作業が設定されます。鉄筋施工図作成作業と鉄筋組立て作業です。前者には1級と2級、後者には1~3級が設けられています。
鉄筋施工技能士は、建築や土木について専門的に学んだことがなくても、実務経験があれば受検することができます。ただし、高校の土木科を卒業しているケースなど、学歴による緩和要件があります。
技能検定に対するとらえ方は業界や職種によって異なりますが、鉄筋工事業は特に「鉄筋施工技能士」の取得を奨励する傾向があるようです。
学科や実技の講習を社内で行ったり、受検費用を会社で負担したりするなど、資格取得のバックアップ体制を整えている会社は少なくありません。また、1・2級鉄筋施工技能士の有資格者に資格手当を支給する会社も多く、職長になる条件として1級鉄筋施工技能士への合格が掲げられている会社もあります。
また、鉄筋施工技能士は、資格の取得によって技能レベルが証明できるだけでなく、許認可関係においても、メリットがあります。
鉄筋工事業の一般建設業の許可を持つ事業者は、営業所に専任技術者を配置し、工事現場に主任技術者を配置することが義務づけられています。
そこで役立つのが、鉄筋施工技能士の資格です。1級と2級の鉄筋施工技能士は、いくつか条件はあるものの、専任技術者や主任技術者になることができる資格です。そういった意味からも、鉄筋施工技能士の有資格者は必要とされています。
型枠施工技能士
最後にご紹介するのは、型枠施工技能士の資格です。
型枠施工の仕事は未経験から始められます。とは言え、ある程度の技術が身についてきたら、まず目指すべき資格は、この型枠施工技能士と言えるでしょう。
建設業界には数多くの資格がありますが、型枠組立作業に必要とされる技能があることを認定する型枠施工技能士は、型枠大工を極めたいのであれば、ぜひ取っておきたい国家資格です。
この技能士資格保有者を歓迎する求人案件も多数みられますので、高く評価されている資格といえるでしょう。
等級は1級と2級があり、2018年からは新たに型枠工事の基本的な技能を持っている方や、これから仕事に就く予定の方などを対象とした3級が加わりました。
型枠工は中高年が中心となって活躍していますが、これからは理論と技能を修得した型枠施工技能士の資格保有者が多くなると予想されています。
あとがき
建設躯体工事は、外壁や内装によって、表面には見えなくなってしまいます。しかし、建物を建物たらしめている重要な作業であり、まさに陰で支えている存在です。
躯体工の方は、待遇やスキルアップのために、今回ご紹介した3つの資格取得を目指してみてはいかがでしょうか。