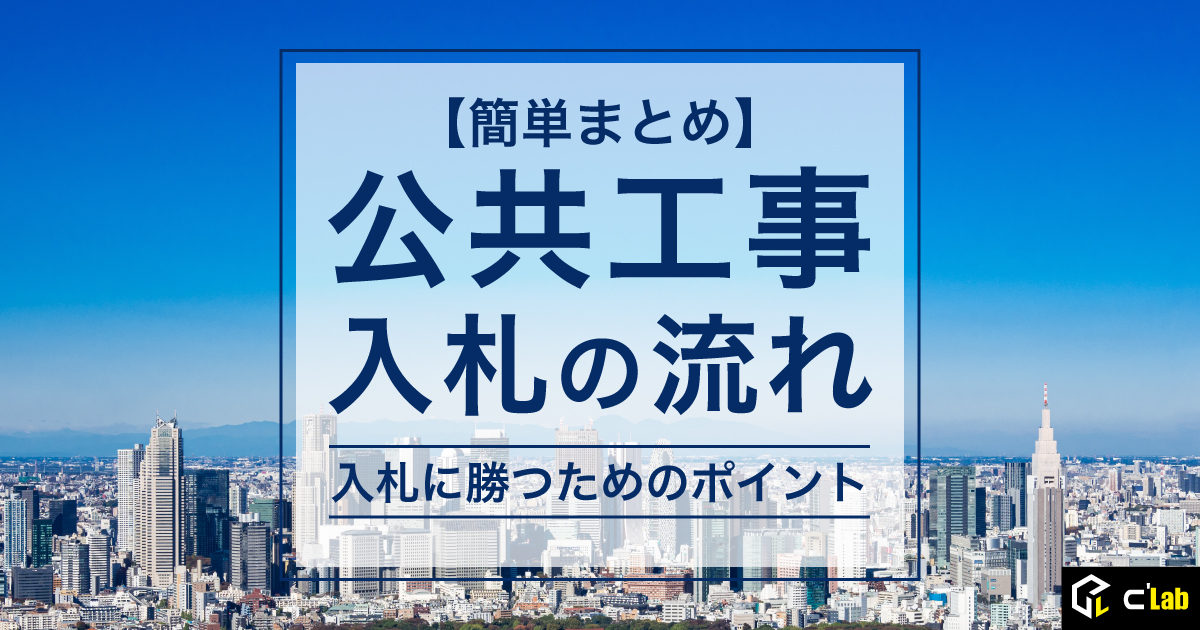
公共工事を受注したいと思ったときに、「初めてなので入札の流れが分からない」と疑問を持つ方は少なくありません。
この記事では、公共工事の一般競争入札の流れと、入札に勝つための3つのポイントを解説します。ぜひ最後までご一読ください。
目次
公共工事の入札とは?
公共工事の入札とは、官公庁や地方自治体が民間の建設業者と契約を結ぶ際に、契約する業者を選ぶ仕組みです。
入札の目的は、誰でも公平に受注できるように、競争の機会を確保することです。
入札によって、公的機関は契約相手を公平に選べます。
また、価格競争によって経済性の追及も可能です。
官公庁や地方自治体の工事を受注した場合、資金の出どころは税金ということになります。
税金を有益に使うためにも、入札は合理的な制度であると言えます。
公共工事の入札の流れを解説!
公共工事の入札には、下記の3つの種類があります。
・一般競争入札
・指名競争入札
・随意契約
公共工事の実績がない建設業者は、まずは一般競争入札から参入しましょう。
ここでは、一般競争入札に初めて参加する場合の流れを、7つのステップに分けて解説します。
1. 事業者登録
入札に参加するにあたり、まずは官公庁や地方自治体が定める事業者登録を行います。
近年、多くの自治体では、さまざまな手続きが電子化されているため、入札の事業者登録にもオンラインシステムが導入されています。
詳しくは各自治体の公式情報をチェックしましょう。
なお、事業者登録の申請時期には以下の2種類があります。
・定期申請
2年に1回を原則として2月ごろに実施
・随時(臨時)申請
年度内に随時実施
いずれの場合も受付期間が定められているため、注意してください。
一般的に、事業者登録の有効期限は2年です。
有効期限が切れた場合は、再度申請する必要があります。
2. 入札案件探し
入札に参加するためには、自社が参入できる入札案件情報の入手が必要です。
入札案件の情報を探す方法は、以下の2つです。
・各行政機関のホームページを一つひとつ閲覧する
・入札情報サイトを利用する
官公庁や地方自治体のホームページには、入札案件の情報が不定期に公開されます。
ホームページを閲覧することで、入札案件を見つけられます。
ただし、すべての行政機関のホームページを閲覧して、入札案件を手作業で探すには、大きな手間がかかり、見落とす可能性もあるでしょう。
その点、入札情報サイトを利用した場合、入札案件を効率よく探すことが可能です。
利用には費用がかかるのがネックですが、その価値は十分あると言えます。
3. 入札説明会への参加
入札に参加するには、入札関係資料を手に入れなければならない場合があります。
入札関係資料は、入札説明会で配られるのがスタンダードです。
また、入札説明会への参加が、入札に参入するための要件となっているケースもあります。
説明会の内容や配布資料には、入札価格を決めるために必要な情報が含まれている場合が少なくありません。
入札説明会には必ず参加し、不明な点が残らないようにしましょう。
4. 必要書類の準備
入札に必要な書類は、入札案件によって異なります。
書類の必要事項を満たさなかったり、記載内容に不備があったりする場合には、入札に参加できない恐れもあります。
入札仕様書などをよく読み、必要書類の準備や記入には抜けや漏れのないよう意識しましょう。
5. 入札価格の決定
入札に参加する際には、入札価格を決める必要があります。
入札説明会の内容なども参考にして、価格を決めてください。
ただし、価格を低く設定しすぎた場合は失格となることもあります。
適正価格で受注できるよう、慎重な価格設定が重要です。
6. 落札者の決定
発注機関(官公庁や地方自治体)によって、落札者(建設業者)が決められます。
価格によって決める最低価格落札方式と、建設業者の技術力や地域貢献度などを考慮して決める総合評価落札方式があります。
7. 契約の締結
案件を落札した業者は、発注機関と契約を結びましょう。
基本的には、あらかじめ提示された契約内容にしたがって契約を締結します。
契約の内容の変更を希望する場合には、入札参加の前に発注機関に相談しておくことをおすすめします。
公共工事の入札で勝つためのポイント
入札に参加するからには、確実に落札して受注したいところです。
一般競争入札に勝ち、案件を受注するためのポイントを3つご紹介します。
1. 競合する建設業者や発注機関の傾向を探る
発注機関によっては、過去の入札案件や入札結果の確認が可能です。
そのため、過去に同じような案件が、どのくらいの価格で落札されたのかという情報を入手できます。
入札案件の相場観や傾向の分析はとても重要です。
また、自社と競合する業者が、入札によって利益を増やしていることはよくあります。
競合業者の落札情報もしっかりとチェックしておきましょう。
2. 入札仕様書について質問する
入札に参加するには必要書類の準備が必要ですが、内容に不備などがある場合は入札に参加できません。
入札の仕様書にあいまいな表現の記載がある場合、発注機関に質問をすることで、自社にとって有利になる具体的な仕様書に修正できる可能性があります。
入札仕様書を熟読し、不明点がある場合は必ず質問することをおすすめします。
なお、入札仕様書についての質問は、メールやファックスでも可能です。
設けられた質問受付期間内に尋ねましょう。
3. 単純ミスを回避する
必要書類の誤字脱字や計算ミスは、複数人のダブルチェックなどによって避けることが可能です。
また、入札説明会の日時や場所、入札自体の時間は、絶対に間違えないようにしましょう。
単純ミスは、発注機関の心証をよくないものにしてしまいます。
念入りな確認を徹底し、ミスが生じないように意識してください。
あとがき
今回は、公共工事の入札の流れや、入札に勝つためのポイントを解説しました。
この記事で紹介した内容が、公共工事受注の実績を手に入れることにつながれば幸いです。